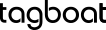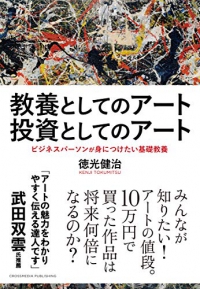コロナ禍が生んだアートバブル
ブームの功罪とその先にあるもの
2020年、新型コロナウイルスの感染拡大が世界を席巻し、日本もまた未曾有のパンデミックに見舞われた。
人々は外出を控え、飲食・旅行・娯楽の多くが制限された。経済も混乱し、株価や不動産市場は一時的に大きく落ち込んだ。しかし、その裏で意外な市場が活況を呈していた。そう、アート市場である。
コロナ禍が生んだアートバブルは、富裕層の「行き場を失った資産」と「アート初心者の爆発的な増加」という二つの要素によって形成された。
そして、オークション市場の拡大が火に油を注ぎ、ギャラリーの乱立がブームを加速させた。しかし、日本が世界でもっともコロナ禍を終わらせるのが遅れたことが、結果的にその反動を大きくし、アート市場は急激に縮小していくことになる。
コロナ禍のアートバブルは、一体どのようにして生まれ、なぜ一瞬のブームに終わってしまったのか。そして、我々はこの経験から何を学ぶべきなのか。
アートは「余ったお金の行き先」だった
コロナ禍で最初に大きく変化したのは、富裕層の資産運用だった。株式市場は2020年3月に大暴落し、不動産も先行き不透明となった。
これまで投資をしていた資産が目減りする恐怖の中で、富裕層は次なる投資先を探し始めた。そのひとつとして注目されたのがアートである。
アートは歴史的に「不況に強い資産」とされ、実物資産であることから「インフレに強い」とも言われる。
このタイミングで、欧米のアートマーケットではすでにデジタルアート(NFT)への投資が過熱しており、日本でも「アート=投資対象」という意識が高まっていった。
また、投資目的だけではなく、「使い道のないお金」がアート市場に流れたという側面も見逃せない。
コロナ禍では旅行も外食もエンタメも制限された。「どうせなら家で楽しめるものを」と考えた人々が、アートを買うようになったのである。
こうして、にわかコレクターが一気に増加し、アート市場は活況を呈した。
オークションが火をつけたアートバブル
この流れにいち早く乗ったのがオークション市場だった。
特に国内大手オークション会社は、コロナ禍で過熱する一部の作品を積極的に取り扱い、価格の上昇を演出した。
結果として、セカンダリーマーケットが活性化し、「アートは売れるもの」という認識が広がっていく。
もともと、日本のアート市場はギャラリー主導の一次(プライマリー)市場が中心だったが、オークションの拡大によって、「転売目的でアートを買う」という新しい層が生まれた。
彼らは、価格が上昇しているアーティストの作品を購入し、短期間で売却することで利益を得ようとした。
この動きが相場をさらに引き上げ、アートバブルを加速させることになる。
そして、この「転売熱」がにわかコレクターの心理を刺激した。「アートを買えば儲かるらしい」という誤解が広まり、投資経験のない層までアート市場に参入したのだ。
原宿に林立したギャラリーと供給過剰の波
このバブルの波に乗ったのが、原宿・渋谷界隈の新興ギャラリーだった。特にイラストレーション系アートや萌え系アートを扱うギャラリー、中国資本のギャラリーが急増し、東京のアートシーンは活況を呈した。
しかし、この動きは必然的に「供給過剰」を招いた。
にわかアートファンの増加により、短期的な売り上げは伸びたが、市場が成熟していない日本では「コレクター層の厚み」が足りなかった。
ギャラリーの数が増えても、それを支えるだけの継続的な購入者が育っていなかったのだ。
バブルの崩壊と市場の急縮小
しかし、日本は世界でもっともコロナ禍を終わらせるのが遅れた国のひとつだった。欧米では2021年半ばから経済活動が再開され、アート市場は徐々に正常化した。
しかし、日本では長引くコロナ対策によって経済回復が遅れ、その反動が一気に訪れた。
外食・旅行・エンタメが再開されると、人々はアートよりも「リアルな体験」にお金を使い始めた。
さらに、金融市場の回復により、富裕層の資産運用は株式や不動産へと戻っていった。これによって、にわかアートファンの購買意欲は急速に冷え込み、バブルが崩壊した。
「転売目的」でアートを買っていた層も、価格が下がるとともに市場から撤退した。オークション価格はピーク時の半分以下に落ち込み、新興ギャラリーの多くが閉店に追い込まれた。
ブームを一過性にしないために
では、このコロナ禍のアートバブルから、我々は何を学ぶべきなのか。
第一に、「にわかブーム」に頼った市場の拡大は、持続性がないということだ。
プチバブル期に増えたコレクターの多くは、長期的なアートファンではなく、一時的な投機家だった。アート市場が安定的に成長するためには、「短期的な転売熱」ではなく、「長く作品を愛し、コレクションする文化」が必要である。
第二に、市場の成長には「継続的な買い手」の育成が欠かせない。ギャラリーは目先の売り上げだけを追うのではなく、アートの価値をしっかりと伝え、真のコレクターを育てるべきだ。
そして最後に、アートの価値は市場価格だけでは測れないということ。コロナ禍が終わった今、アートは「投資対象」ではなく、「文化」として根付くことが求められている。
一時のブームに踊らされるのではなく、アート市場を成熟させるために、今こそ本質的な議論が必要なのではないだろうか。
コラム著者のX(Twitter)はこちら
https://newspicks.com/topics/contemporary-art/
2025年2月21日(金) ~ 3月11日(火)
営業時間:11:00-19:00 休廊:日月祝
※初日2月21日(金)は17:00オープンとなります。
※オープニングレセプション:2月21日(金)18:00-20:00
入場無料・予約不要
会場:tagboat 〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町7-1 ザ・パークレックス人形町 1F
tagboatのギャラリーにて、現代アーティスト手島領、南村杞憂、フルフォード素馨による3人展「Plastics」を開催いたします。「Plastics」では、表面的な印象や偽りの中に潜む本質を提示した3名のアーティストによる作品を展示いたします。